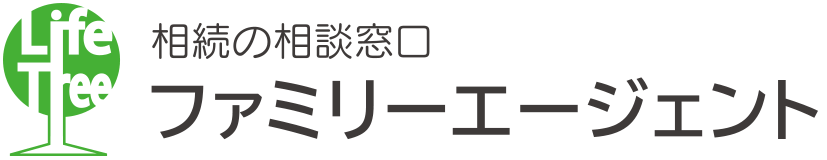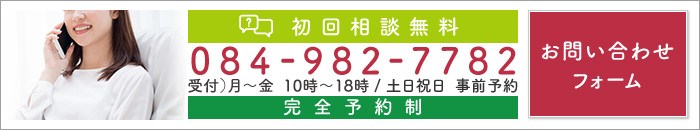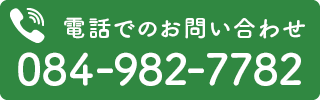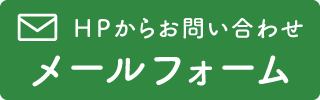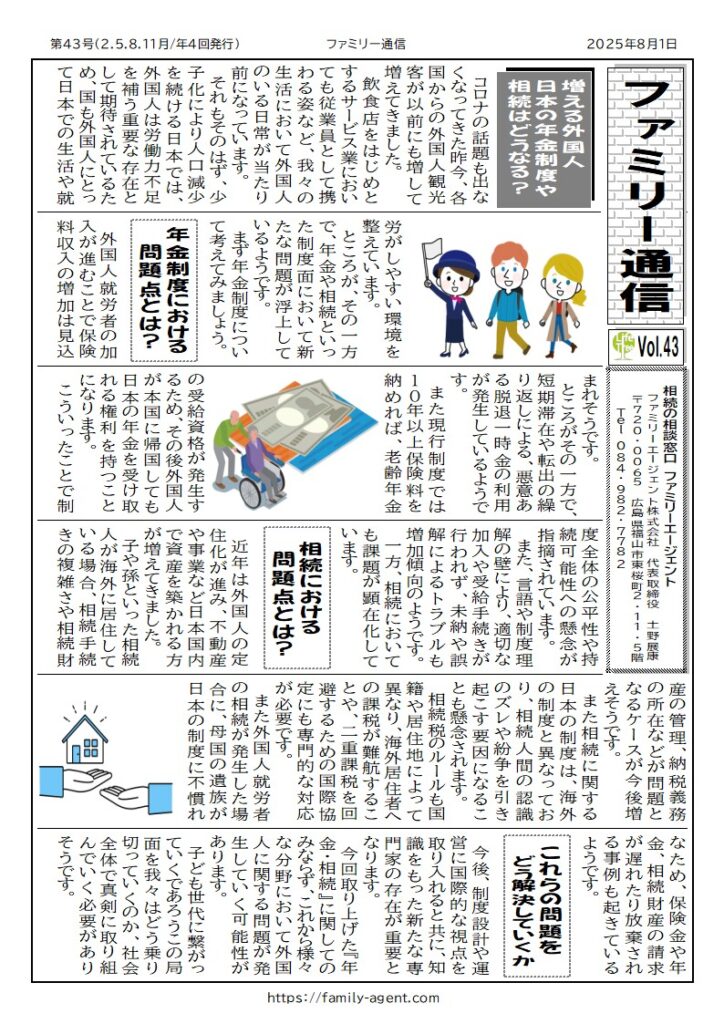
コロナの話題も出なくなってきた昨今、各国からの外国人観光客が以前にも増して増えてきました。
飲食店をはじめとするサービス業においても従業員として携わる姿など、我々の生活において外国人のいる日常が当たり前になっています。
それもそのはず、少子化により人口減少を続ける日本では、外国人は労働力不足を補う重要な存在として期待されているため、国も外国人にとって日本での生活や就労がしやすい環境を整えています。
ところが、その一方で、年金や相続といった制度面において新たな問題が浮上しているようです。
まず年金制度について考えてみましょう。
外国人就労者の加入が進むことで保険料収入の増加は見込まれそうです。
ところがその一方で、短期滞在や転出の繰り返しによる、悪意ある脱退一時金の利用が発生しているようです。
また現行制度では10年以上保険料を納めれば、老齢年金の受給資格が発生するため、その後外国人が本国に帰国しても日本の年金を受け取れる権利を持つことになります。
こういったことで制度全体の公平性や持続可能性への懸念が指摘されています。
また、言語や制度理解の壁により、適切な加入や受給手続きが行われず、未納や誤解によるトラブルも増加傾向のようです。
一方、相続においても課題が顕在化しています。
近年は外国人の定住化が進み、不動産や事業など日本国内で資産を築かれる方が増えてきました。
子や孫といった相続人が海外に居住している場合、相続手続きの複雑さや相続財産の管理、納税義務の所在などが問題となるケースが今後増えそうです。
また相続に関する日本の制度は、海外の制度と異なっており、相続人間の認識のズレや紛争を引き起こす要因になることも懸念されます。
相続税のルールも国籍や居住地によって異なり、海外居住者への課税が難航することや、二重課税を回避するための国際協定にも専門的な対応が必要です。
また外国人就労者の相続が発生した場合に、母国の遺族が日本の制度に不慣れなため、保険金や年金、相続財産の請求が遅れたり放棄される事例も起きているようです。
今後、制度設計や運営に国際的な視点を取り入れると共に、知識をもった新たな専門家の存在が重要となります。
今回取り上げた『年金・相続』に関してのみならず、これから様々な分野において外国人に関する問題が発生していく可能性があります。
子ども世代に繋がっていくであろうこの局面を我々はどう乗り切っていくのか、社会全体で真剣に取り組んでいく必要がありそうです。